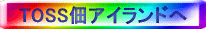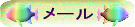国語テストの答え方指導8
接続詞の答え方
小学校国語全学年対象
遠藤真理子
2007.11.19作成(2008.2.3更新)
今回は、接続詞・接続助詞の答えの求め方と指導法について述べる。
テスト75枚(約750問)中、17問がこの問題である。出題率は2%というところだ。
実際に見てみよう。
1.問題例
わたしたちの生活の便利さを支えている物質によって、今、地球上の生命が危険にさらされようとしているのである。
〔 〕、一九八五年以降、たびたび国際会議が開かれるようになった。 |
問い1 〔 〕に合う言葉を選び、○をつけなさい。
( )しかし( )また ( )そこで( )なお
問い2 前後の事がらの関係を考えて、( )に合う言葉を□から選んで書きましょう。
①先生が注意した( )、わすれ物をした人がいる。
②かさを持っていけ( )、夕立が来てもだいじょうぶだ。
③今年は雨が少ない( )、水不足が心配だ。
問い3 の言葉は、文を正しくつないでいません。正しくつなぐ言葉を二つずつ書きなさい。
①父は、夜おそくならないと帰らないと思います。しかし、母も用事で出かけています。
( )( )
②きのうからひどいかぜをひています。そして、今日は学校を休んだのです。
( )( )
| また、ここでは、空気の調節をして、ごみがよくもえるようにしていました。〔 〕、けむりをすい取るそうちもくふうしているそうです。 |
問い4 〔 〕に合う言葉を、□からえらんで書きなさい。
17問からの抜粋である。問い3のような記述式はこれだけで、あとは全て選択肢付きであった。
どれが何年生の問題かちょっとお考え頂きたい。
実は、問い1が6年、問い2が5年、問い3と4が4年のテストに出ていたのである。
前回にも書いたが、内容はともかく解答方法については学年の系統性などほとんどないように感じられる。
2.答えの見つけ方の指導
接続詞の問題に限らず、選択肢付きの問題は、代入して答えを探すことを教える。
生活科になってからというもの、テストに慣れていない新3年生が増えた。社会や理科のテストをしてみると驚くほど答え方が分かっていないことが分かる。そこで、社会や理科のテストが、答え方指導の絶好の場となる。
特に、社会のテストでは選択問題が多い。例えば次のような問題。
商店街では、( )をつくって雨をふせいだり、( )をしてお客さんをふやすくふうをしています。
道路 駅 アーケード 多い 少ない 安売り |
答えを選ぶときは、( )の中に一つ一つ言葉を入れて読んでみます。
商店街では、道路をつくって雨をふせいだり・・・・
商店街では、駅をつくって雨をふせいだり・・・・
商店街では、アーケードをつくって雨をふせいだり・・・・
商店街では、多いをつくって雨をふせいだり・・・・ |
かなりおかしな文もできるため、子どもたちから笑いが起こる。
答えが分かったら( )に書きなさい。
この答えはもう使ってしまったので、×を付けて消しておきます。 |
問題を読んで答え方の説明をしながらさせると、10分でテストも終わってしまうし当然点数もアップする。
初めてテストで接続詞の問題が出てきたときもこのように指導している。
私は小学生の頃、極めて社会科のテストの点が良くなかった。担任の先生が「社会のテストは国語のテストのようなものです」とおっしゃっていた意味が今はよく分かる。なにしろ、代入して日本語として正しい文になっていれば正解になるからだ。当時、代入法を知っていれば、社会のテストだってもっと良かったはずなのに・・・・。
3.記述式の問いに答える力を付けるには
問い3のような問いに答える力を付けるには、同じ意味の接続詞が複数あるということを授業の中で教えておかなければならない。次のような指導をする。
次の文をノートに写しなさい。
A.雨がふってきました。( )、かさをさしました。
( )に合うつなぎ言葉を書きなさい。 |
発表させる。だから・それで・それだからなどが出される。「私は」などの言葉も出されるが、「つなぎ言葉ではありません」と言ってくどくど説明はしない。
| B.雨がふってきました。( )、かさを持っていません。 |
しかし・でも・だが・なのになどが出る。
Aに入る接続詞はBには入らない。逆もしかり。高学年なら、AとBの文はどのように違うのかを考えさせる。
「Aは、先の文が後の文の理由になっている。Bは、後の文が前の文と逆の内容になっている。」というような意見が出されるだろう。