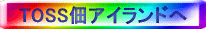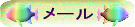国語テストの答え方指導6
言葉の意味を問う発問
小学校国語全学年対象
遠藤真理子
2008.2.3更新
国語テストの言語の中には、言葉の意味を問うものがある。
「4.名詞で答える問い」「5.動詞で答える問い」のページで、名詞・動詞で答える発問があと一つある、と書いた。実は今回の「言葉の意味を問う発問」の中に出てくる。
今回はその答え方について。
小学校のテストでは、大抵が選択肢つきである。
次の言葉の意味を選び、記号を書きなさい。
① 目標・・・・( )
② 達成・・・・( )
ア はたさなければならない仕事。
イ やりとげること。なしとげること。
ウ なしとげようとする、めあて。
エ 大体の見当をつけておくこと。 |
このようになっていれば、少なくとも記号さえ書けば当たる確率はある。
さて、問題は選択肢のない場合である。どのように答えたらよいのであろうか。
次の言葉の意味を書いてみてほしい。
答えを書く前に、ヒントを。
①見学、②先生は名詞、③叫ぶ、④口をすべらせるは動詞、⑤強いは形容詞である。品詞によって、答えの文末が違ってくるのである。
【解説】
表現は色々あるので、文末に注目して見ていただきたい。
①実際に見て学ぶこと。
「実際に見て学ぶ。」では不正解。「見学」は名詞であるから、答えも名詞で答える。文末に「こと」と付けると名詞になる。
②勉強などを教えてくれる人。
「勉強などを教えてくれる。」では、動詞になってしまうので不正解。では、「こと」を付ければよいのだろうか。「勉強などを教えてくれること。」となり、確かに名詞にはなるがこれは事柄になってしまうので意味が違ってくる。「先生」とは、「人」である。この場合は文末に「人」と付けるのが適切である。ついでに、鉛筆のような物の意味を聞かれたら、文末には「物」、赤の意味を聞かれたなら文末には「色」、というように、事物の種類が分かるような文末にすると良いことを付け加えておく。
③大声を出す。
意外と「大声を出すこと。」と書いてしまうことがあるのではないだろうか。特に口頭で発問したときなど、「叫ぶとはどういうことですか。」などと聞いてしまうから「大声を出すこと。」と答えてしまう。この場合はこれで正しいのだが、度重なるとテストでも同じように書いてしまうことになる。発問するときも「叫ぶの意味を書きなさい。」と指示し、動詞の意味を聞かれたら動詞で答えることをきちんと指導しなければならない。
④思わず言ってしまう。
「すべらせる」は動詞であるから、文末も動詞にする。やはり文末に「こと」「様子」などと付けたくなってしまうが不要である。「口をすべらせるとは、どんな様子ですか。」と聞かれたら「様子」とつけるが、意味を聞かれた場合は動詞で答えるのが正しい。
⑤ちからがある。丈夫である。
形容詞や副詞の意味となると、つい文末に「様子」と付けてしまうことが多い。慣例的に間違いとまでは言えないと思うが、付ける必要はないと考えている。
余りに瑣末な部分にこだわりすぎた気もするが、意識して見てみると選択肢の文末の品詞が言葉の品詞と合っていないこともある。問題集やワーク選びのポイントになるかもしれない。
【演習問題】
次の言葉の意味を書きましょう。
①美 ②美人 ③美味 ④美しい ⑤きらめき ⑥きらめく |
【解答】
①きれいなこと。きれいなもの。
②美しい人。きれいな人。
③美味しい味。
④きれい。かわいい。愛らしい。
⑤光り輝くこと。光り輝くもの。
⑥光り輝く。
向山氏は、「辞書作り」と称して言葉の意味を書かせる指導をするそうである。
まず簡単なところから、色を取り上げる。
「赤」「黒」「白」「青」などは、たとえを使えば簡単に書くことができる。
「赤」に対して子どもたちは、「血のような色」「夕日のような色」と答える。文末に「色」とつけて、名詞になるように答えている。
次に「東」「西」などの方角の意味を問う。これにも、「太陽の昇る方」「太陽の沈む方」と、文末に方角を意味する「方」をつけて名詞にして答える。
文末がきちんとしていなければ、この時点で「色の意味だから、こういう色、と答えます。」「方角の意味だからこっちの方、というように答えるといいね。」と指導すれば良い。名詞だの動詞だの、あまり細かく教えなくてもよいだろう。
意外と難しいのが「右」「左」の意味。これも方向であるから「こっちの方」と答えさせる。
体の部分の意味を聞くのも面白い。文末には「~~する部分」とつけて名詞にさせる。
名詞の意味を色々と書かせたところで「名詞の意味を聞かれたら名詞で答えよう。」とまとめるのである。
それじゃあ、ということで、次に動詞の意味を考えさせていく。子ども達にはテストに出ているような言葉ではなく、できるだけ単純な言葉の意味を考えさせると、楽しくしかも無理なく文末の指導ができる。